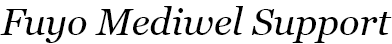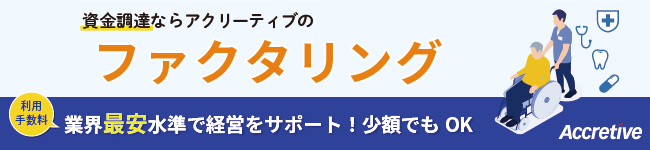<著者> 株式会社ヘルプズ・アンド・カンパニー 代表取締役 西村 栄一
見出し2:17上下線
介護事業が安定したら、次に今あるレベル1を10 に、そして100 にしていくことが、経営者としての使命です。
ところで、自事業所はなぜ、今、取り引きしている「ケアマネジャー」にお付き合いいただけているのか、サービス提供する「利用者」はどうして自事業所のサービスに満足していただけているのか、思いをめぐらしたことはありますか?
そのあたりを経営者はもちろん理解しておいていただきたいし、そのサービス提供の主体である職員はどうイメージしているのかまで把握しておくべきです。
さらには、その利用者が、数年後もサービスを利用している姿まで具体的にイメージすることが大切です。安定化している今だからこそ、ケアマネジャーに今後について聞いてみる絶好の機会かもしれません。
これは先を見据えたバックキャスティング手法で、逆算の思考でもあるのです。
たとえば、訪問介護であれば1対1であるからどのような介護を提供しているのかはイメージしやすいと思います。
一方で、通所介護ですと複数の方々が異なる1日の過ごし方をされているので、その方々に合った過ごし方を考えてみてください。「全く考えてもみなかった」という方はいないと思います。
ですから、「うちの事業所はどんな方でも受け入れています」「どんな人でもウェルカムです」なんて言っているうちは、自事業の姿が見えていないと思ってください。
経営が安定化したら、進化、発展させていきたいのかなど含めて、次はどのような事業所にしたいのかを考えましょう。さらにイメージを言葉にする「コンセプトの確立」が最も重要な要素です。
それを考えるきっかけとして、「自分の地域にはないオンリーワン」のサービスを考えることも一つの案です。ただし、そのオンリーワンが、地域住民やケアマネジャー、医療関係者、ひいては、利用者のためになるのかを考えましょう。
進化、発展するのに必要な受け入れとなりえるのか、それとも誰も気づかなかった潜在的なニーズもあるのか、それは自事業所の職員にできることなのか(これが一番大事)、などです。
安定化の次に、進化、発展させていく方向としての正解ではなくとも、ベターなコンセプトであるかどうかの見極めは経営者としてとても重要です。コンセプトの選び方としては、対象者をどう考えるかが挙げられます。
たとえば、利用者のADL状態を軸に置いた場合、より重度な方を受け入れるのか、それとも、軽度者をはじめとした身体介護を必要としない方へのリハビリなのかということです。また、高所得者層、中間層、低所得者層など、生活のレベルでサービス内容を変えることもできます。
また、サービス内容にこだわることで、差別化もできます。一般的にデイサービスでの昼食は安くても300円で、高いところでは700円以上というところが平均なのですが、「一律100円」というところがあります。
メニューも一定のレベル以上のものを出しているところを見ると、昼食だけでは赤字になっているのではないかと予想できます。しかし、これにより「低価格で高レベルな食事の提供」といった具合に、コンセプトが明確になります。利用者一人当たりの単価は下がりますが、稼働率は間違いなく上がります。
なお、そこには定員稼働率70%での黒字化ではなく、90%を達成してやっと黒字化する、といった具合のリスクが存在しますし、コンセプトを明確にすることでリスクが生じるというのはあり得ると思います。
経営とリスクは背中合わせであり、それこそ「覚悟」です。
監修:㈱日本医療企画
制作年月:2022年3月
PROFILEプロフィール
株式会社ヘルプズ・アンド・カンパニー 代表取締役 西村 栄一
関連サービス
👉経営の安定化を図るために
介護用品・福祉用具等の新調や入れ替えなど、経営においては設備投資が必要となり、コスト負担も大きいものです。
そこで、費用の平準化のためにファクタリングの活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。コストの把握も容易になり、借入枠の温存も可能なため、安定した事業運営を行うことができます。
ファクタリングによる資金調達をご検討されている方は、豊富な取引実績があるアクリーティブ【芙蓉リースグループ】に是非ご相談ください。