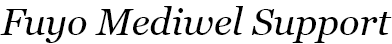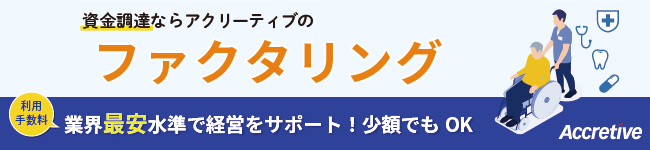<著者> 北海道介護福祉道場あかい花 代表 菊地雅洋
生産労働人口が大幅に減り続けているわが国では、全産業で人手不足が深刻化しています。
そのなかで他産業より待遇が悪いと印象づけられている介護事業者には、募集をかけても応募してくる人材が少なく、より深刻な人材不足に直面しています。
それがゆえに介護事業者の一部では、応募してきた人の能力チェックを十分に行わないまま、機械的に採用してしまう傾向が強まっています。そうして採用された人のなかには、対人援助に不向きで、教育の力が及ばないスキルの低い人も存在することになります。
対人援助は人の感情に寄り添うサービスであるため、マニュアルに沿った機械的な作業だけを行っていればよい仕事ではなく、利用者の心理状態を慮りながら、自ら考えて裁量を働かせなければならない場面もあります。決して単純作業ではなく、知的労働です。
そのような職業であるにもかかわらず、採用時の選択を放棄して、対人援助に不向きな人を採用すると、結果的にはほかの職員に負担がかかり、能力のある職員がバーンアウトします。
さらに能力がない職員によって介護サービスの現場で不適切なサービスが生まれ、そうした行為がエスカレートして虐待に繋がるなどの深刻な経営リスクに直結する場合があります。
そういう意味では、人材不足だからこそ採用はより慎重に行い、かつ介護事業者自らが、人を育てる組織としてのガバナンスを確立しなければならないのです。しかし、応募してきた人の能力を採用段階ですべて的確に見抜くことは不可能です。
面接担当者がどのように努力しようと、わずか一度の面接で、人の能力や性格を見抜くことはできず、良かれと思って採用した人物が期待外れで、仕事の成果を挙げられないばかりでなく事業運営上の障害となることもあります。
事業者としてこのような問題にどう対処すべきでしょうか。それは試用期間という規定を活用することでしか解決しません。
試用期間は労働基準法等には定めがない、事業者の任意的事項です。よって試用期間の定めのない事業者も存在しますが、この期間は採用した職員の適格性・協調性を確認する期間であり、教育期間でもあるという理解のもと、必ず就業規則等に定めておくべきです。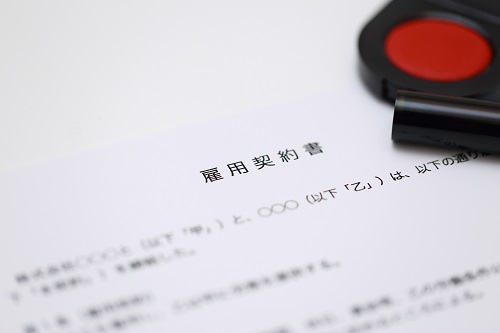
ただし試用期間であっても、すでに労働契約は成立しているので、解雇権は乱用できません。しかし試用期間中の解雇については、通常の解雇よりも広い範囲でその自由が認められており、合理的理由により使用者が解約権を行使できるものと解釈されています。
過去の判例で認められた解雇事由としては次のようなものがあります。
能力の大幅な不足
入社前に期待していた能力が入社後にはまったく発揮されず、担当業務をいくつか変えても勤務成績が上がらない場合が該当
勤務態度の不良
入社後の勤務態度が極めて悪く、協調性もなく、周囲の業務にも悪い影響を与える場合が該当
このような解雇事由にあたるかどうかを試用期間中に適切に判断するには、試用期間中にOJTを中心にして教育を担当する現場リーダーの判断が必要不可欠となります。
リーダーは新入職員に業務や規則を教えるだけではなく、試用期間という限定された期間内に、その職員が組織にとってふさわしい人材として成長できるかを見極め、対人援助に不向きと判断した場合は、上司に報告しなければなりません。
だからこそ介護事業者には、判断能力のあるリーダーを育てることが何よりも重要となってくるのです。そのことがガバナンスの肝になってくるとも言えるでしょう。
監修:日本医療企画
制作年月:2018年10月
PROFILEプロフィール
菊地 雅洋
北海道介護福祉道場あかい花 代表
(きくち・まさひろ)●1960年、北海道上川郡下川町下川鉱山に生まれる。北星学園大学文学部社会福祉学科卒業。特別養護老人ホームの施設長を経て現職。自身が管理する「介護福祉情報掲示板」(表板)は屈指の情報量を誇る掲示板。ブログ「Masaの介護福祉情報裏板」では一味違った切り口で、福祉や介護の現状や問題について熱く語る人気ブロガー。
関連サービス
「安定した経営を、ファクタリングサービスでサポートいたします」 👉詳細はこちら
「ファクタリング」は資金使途自由で、スピーディーな現金調達が可能です。
- 新規事業所をオープンしたいが、新たな借入は避けたい・・・
- 賞与資金や退職金など、一時的にまとまった資金が必要となり、調達に苦労している・・・ etc.
このようなお悩みをファクタリングサービスでサポートいたします。
ぜひ一度、ご相談ください。