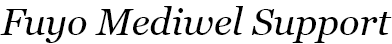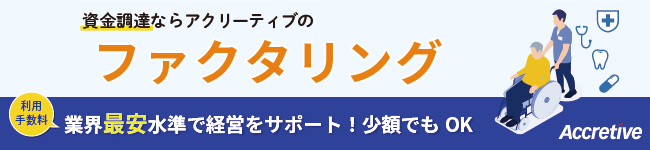<取材先> 合同会社TYパートナーズ 代表社員 筒井祐智
元介護事業経営者の視点から
介護事業者向けコンサルティング事業などを行うTYパートナーズ(東京都港区)。
全国110ヵ所超でデイサービスを展開する早稲田エルダリーヘルス事業団の元社長である筒井祐智代表に、持続可能な介護事業経営に向けた、資金調達手法や補助金・助成金の活用について伺いました。
01負債による資金調達
まず、資金調達の手法についてですが、大きく4つに分かれます。
1つ目は「負債による調達」。金融機関や自治体の制度融資、ノンバンク(ビジネスローン)、私募債などからの借入がこれに当たります。
金融機関からの融資について、具体的には、都市銀行や地方銀行、信用金庫、信用組合、政府系金融機関(政策金融公庫等)など。
創業間もない事業者は銀行からの融資を受けるのが難しい場合もあり、信用保証協会を利用した融資や、政府系金融機関の創業融資を活用するケースも多くあります。福祉に特化した仕組みとしては、福祉医療機構(WAM)による福祉貸付事業の活用もできます。
2つ目は「自治体の制度融資」。地方自治体と民間金融機関、信用保証協会の3機関が連携して実行する融資です。創業間もない事業者や初めて融資を受ける事業者でも利用しやすいというメリットがあり、新型コロナウイルス感染症関連の制度もあります。
3つ目が「ノンバンク(ビジネスローン)」。銀行以外の金融機関であるノンバンクは、信販会社、消費者金融等が提供する事業資金に特化した金融商品です。金融機関からの調達に比べ、調達にかかる時間は短いが金利が高く返済の負担が大きいのが特徴。介護給付費を担保に借入を行うといったローンもあります。
そして4つ目「私募債」は、企業が発行した社債を、投資家や取引先など50人未満の人々に販売し調達を行う手法です。手続きが公募債に比べて簡易で、保証人を立てる必要がない等のメリットある一方で、償還時の一括返済や調達コストが高いといったデメリットもあります。
02資産の現金化による資金調達
次に、資産(債券や不動産)を売却することによる調達手法です。
まず「債券の流動化(ファクタリング)」ですが、これは介護報酬債権をファクタリング会社に譲渡することで資金を調達します。通常2ヵ月の介護報酬債権の現金化を早期化できる一方で、事務手数料等がかかるため、満額を受け取ることはできない点がデメリットと言えます。
また、短期的な活用にとどめない場合、長期的には資金繰りを悪化させる可能性があるので注意が必要です。
そして、「不動産のオフバランス」。保有している不動産を売却して資金調達を行いますが、売却した不動産を不動産会社より借りる(リースバック)ため、そのままの拠点で運営を継続できます。昨今では、クラウドファンディングの活用事例も増えてきました。これによる施設の流動化(オフバランス)も見られます。
03資本の増強
さらに、「第三者割当増資」等により資本を増強する手法もあります。
負債ではないので返済の必要がない点がメリットですが、出資者による経営への関与・干渉が想定されるため、自由な経営が難しくなる可能性があるでしょう。
04助成金・補助金の活用
また、助成金や補助金の活用は非常に重要です。事業の発展や雇用促進、設備投資等を目的として国や地方公共団体が提供する資金であるため、融資と違い、返済の必要がありません。申請の採択から入金までに時間は要しますが、活用しない手はないでしょう。
例えば新型コロナ関連の貸付は、厚労省では現在約2兆円の規模で実行されています。なお、助成金と補助金の違いについて、助成金は厚労省管轄のものが多く、雇用の安定や職場環境の改善を目的とした制度であり、補助金は、主に経済産業省管轄で、創業支援や設備投資関連の事業が対象となります。
具体的に、「人材雇用」「人材育成」「従業員の待遇向上」「職場環境の整備」「介護機器の導入」に分けて、活用可能な助成金・補助金を見てみましょう。
まずは「人材雇用」関連の助成金です。「キャリアアップ助成金(正社員コース)」は、従業員の待遇や福利厚生制度を充実させたいと考える経営者を支援する制度。就業規則や労働協約等に基づいて、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換・直接雇用した場合に助成金が支給されます。
例えば有期雇用を正規雇用へ転換した場合では、1人あたり57万円~72万円支給となります。
ほかにも、職業経験・技能等の理由で安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークや職業紹介事業者等からの紹介を受けて一定期間試行雇用した場合に助成金を支給する「トライアル雇用助成金」制度。
また、高年齢者や障害者などの就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主を支援する「特定求職者雇用開発助成金」、中途採用による雇用の活性化を目的とする「中途採用等支援助成金」、65歳以上への定年の引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う場合に支給される「65歳超雇用推進助成金」等があります。
次に、「人材育成」関連の助成金を見てみましょう。
「人材開発支援助成金」は、職業訓練などの人材開発にかかった費用の一部を支給する助成金です。岸田政権が掲げる経済政策「新しい資本主義」において、「人への投資」が第一の優先課題として挙げられたことを受け、令和4年に「人への投資促進コース」が追加され、現在計8つのコースが用意されています。
ほかに、非正規雇用労働者のキャリアアップを促進する規則などを導入・推進する事業者を支援するための「キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)」や、非正規雇用労働者と正規雇用労働者に共通する諸手当に関する制度を策定する事業者の支援を目的とした「キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)」等があります。
「従業員の待遇向上」関連では、仕事と家庭を両立できるような環境づくりを推進するための「両立支援等助成金」、「職場環境の整備」関連では、中小企業団体が従業員の労働環境の向上や人材の確保を行い、雇用管理や雇用創出を行うことを推進する「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」も活用できます。
「介護機器の導入」に関する補助金には、例えば「IT導入補助金」があります。中小企業および小規模事業者が業務改善のためにITツールを導入する際、その経費の一部を補助することでこれらの施策を支援するためのもので、A類型とB類型に分かれており、B類型のほうが求められる条件のハードルが高い分、支給される補助額も高くなっています。
補助対象はソフトウェア費用、クラウド利用料、ITツール導入関連費用。補助額はA類型で30万~150万円、B類型で150万~450万円(いずれも補助率は1/2以内)です。ほかに、「ICT補助金」「介護ロボット導入支援補助金」などがあります。
05情報をキャッチすることが重要
助成金・補助金は、廃止になるものや新たに追加されるものがあり、管轄も各省庁、都道府県、自治体等様々で情報源も異なります。こうした情報に常にアンテナを張り、いち早くキャッチし続けることが重要です。
WEB上での探し方としては、①厚労省、経産省、内閣府等の省庁のHPで探す②各自治体のHPで探す③中小企業基盤整備機構が運営する「J-Net21」サイトで探す――等の方法で、地道に情報を集める必要があります。
介護業界では、「人材関連」「介護機器導入」に活用できるものが多くありますので、自社での取り組みに適用できる助成金・補助金を利用しない手はありません。
持続可能な介護事業経営のために、資金調達や助成金・補助金の活用に関する知識を常にアップデートしておくことが重要でしょう。
※本記事は、㈱高齢者住宅新聞社主催の、9月13日に開催した介護事業者向けセミナー「介護事業者に必要な財務・会計知識~持続可能な介護経営のために~」の内容を編集し作成したものです。
取材年月:2022年9月
PROFILEプロフィール

合同会社TYパートナーズ 代表社員 筒井祐智
(つつい・よしとも)●福岡市出身。慶應義塾大学法学部を卒業後、富士銀行を経て、医療法人に入職。
事務・管理業務に従事した後、グループ内の医薬品開発企業の経営企画責任者としてIPO、M&A等を主導。
その後、早稲田エルダリーヘルス事業団 代表取締役を務め、日本デイサービス協会理事、全国介護事業者連盟東京支部副支部長等を歴任。
関連サービス
ファクタリングサービスの活用で、経営の安定化を図りませんか? 👉ご相談はこちら
*特徴*
その1 |「ファクタリング」は、短期間で資金使途自由な現金調達が可能です。
その2 |また、決算書上の「負債」にあたらないため、財務状況への影響も最小限です。
▽新規事業所の開設や設備投資を行いたいが、新たな借入は避けたい
▽賞与資金や退職金など、一時的にまとまった資金が必要となり、調達に苦労している
ーーこのようなお悩みをファクタリングサービスでサポートいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
(芙蓉リースグループ)